最近「なんだか買い物するたびにレジでドキッとする…」そんな風に感じたことはありませんか?
実際、日本の総務省「消費者物価指数(CPI)」によると消費者物価指数はこの2年間で約3.5%上昇。特に食料品は5.8%、電気・ガスなどのエネルギー関連は7.2%も値上がりしており、4人家族の家庭では月の支出が約12,000円も増加したというデータも出ています。
とはいえ、「収入はほとんど増えていない」…という方が多いのではないでしょうか。その結果、貯金できない・赤字が続くという家庭も珍しくありません。
この記事では、そんな「物価高時代でも家計を赤字にしない」ための節約術と収入アップのアイデアを17個ご紹介します。どれも今日からすぐに取り組めるものばかりなので、一緒に家計を見直していきましょう。
家計の現状把握と見直しの基本ステップ

家計簿診断テスト: あなたの家計は大丈夫?5つのチェックポイント
まずは簡単な家計簿診断テストを行なってみてください。以下テストで3つ以下しかチェックできない場合は改善の余地があるので、今すぐ家計の可視化に取り組みましょう。
□ 固定費と変動費の割合を知っている
□ 過去3ヶ月分の家計状況をグラフ化できる
□ 予期せぬ出費に対する緊急資金がある
□ 支出トップ3項目が何か即答できる
固定費と変動費の割合が分かれば、どこを削減すべきかの優先順位が明確になります。理想的な比率は、収入の50%を固定費、30%を変動費、20%を貯蓄に充てることです。
また、緊急資金は最低でも生活費3ヶ月分を目安に確保しておくのが家計の安定につながります。多くの家計破綻は想定外の出費が原因です。
支出の可視化:家計簿アプリを使用
家計管理の第一歩は「見える化」です。おすすめは家計簿アプリを使うこと。なかでも「マネーフォワードME」は自動連携機能が備わっており、入力の手間を削減できるので便利です。
また、銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で取引を記録するため、忙しい方に最適です。初期設定に30分ほど時間をかければ、その後はほぼ自動で家計簿が完成しますよ!
固定費と変動費の区別: 「まず見直すべきは固定費」という原則
家計改善で最も効果的なのは、変動しにくく毎月継続的に発生する「固定費」の見直しです。保険・通信・住居費・サブスクなどは、一度の契約見直しで年間10,000円以上の節約が期待できます。
以下の手順を使えば、誰でも2時間で家計の現状を“見える化”し、改善ポイントが明確になります。
| ステップ | 作業内容 | 目安時間 |
|---|---|---|
| ① | 過去3ヶ月分の通帳・クレジット明細・レシートを用意 | 30分 |
| ② | 支出を費目別に分類し、それぞれの合計を算出 | 30分 |
| ③ | 固定費と変動費に分けて集計し、支出の比率を確認 | 30分 |
| ④ | 削減できそうな項目に優先順位をつけ、改善プランを立てる | 30分 |
たった2時間で、ムダな支出の“見える化”と優先順位付けができ、家計改善の第一歩を踏み出せます。
また、変動費節約は日々の努力が必要ですが、固定費削減は一度の見直しで継続的効果があります。住居費・通信費・保険料・サブスクなど、契約の見直しを最優先しましょう。
固定費削減の即効テクニック|節約術の最重要ポイント

住居費: 住宅ローン見直しと家賃交渉術
住宅ローンは現在の低金利を活かした借り換えで、年間10万円以上の節約が可能です。実際に0.5%の金利差で3,000万円・残り25年のローンなら、約90万円の総返済額削減になります。賃貸の場合は、契約更新時に「長期居住」や「即時契約」をアピールすると家賃交渉が成功するケースも。
住宅ローン借り換えのベストタイミングは、金利差が0.5%以上、残債が1,000万円以上、残り返済期間が10年以上の場合です。ただし、手数料や保証料も考慮する必要があります。一般的に借り換え手数料は10〜15万円程度かかるため、これを考慮しても3〜4年で元が取れる計算になれば、借り換えの価値があります。特に変動金利から固定金利への見直しは、将来の金利上昇リスクにも備えられる利点があります。
賃貸物件では更新料の交渉も重要です。更新料を半額にできれば2年契約で家賃1ヶ月分の節約になります。交渉の際は「周辺相場」を調査して資料を用意し、長期入居の意思と良好な入居実績をアピールするのが効果的です。
また、新規契約時には初期費用(敷金・礼金)の交渉余地があることも覚えておきましょう。特に空室期間が長い物件や、冬季など閑散期は家主側も交渉に応じやすくなります。
保険料: 不要な特約カットで年間5万円削減
多くの家庭では、知らず知らずのうちに保険の重複や不要な特約に加入しています。特に医療保険の特約や子どもの学資保険の見直しで、年間5万円以上の削減に成功した例は少なくありません。保険見直し専門のFPに相談するのも一案です。
保険の見直しで最初にチェックすべきは「重複加入」です。例えば、生命保険と医療保険の両方に「三大疾病特約」が付いていないか、クレジットカード付帯の保険と個別に加入している保険が同じ補償内容かどうかなど。
また、死亡保障額が必要以上に高くなっていないかも要確認ポイントです。家計を支える人の収入の3〜5年分が一般的な目安とされています。
特に見直し効果が高いのは特約部分です。医療保険の先進医療特約や入院時の差額ベッド代特約など、実際には使う可能性が低い特約を外すだけで、月々1,000〜2,000円の節約になることも。
また、子どもの学資保険は貯蓄性重視のタイプより保障重視のシンプルなタイプに切り替えることで、掛け金を30%程度削減できるケースがあります。保険の見直しは専門知識が必要なため、無料相談できるFPを活用するのがおすすめです。年に一度は保険証券を取り出して内容を確認する習慣をつけましょう。
通信費: 格安SIMへの乗り換えで月3, 000円削減成功事例
大手キャリアから格安SIMへの乗り換えると、月々の料金を非常に安く抑えられます。4人家族で1人あたり6,000円使っていれば合計で24,000円。プランにもよりますが、格安SIMが約3,000円だと仮定した場合、4人で12,000円になります。
テザリング機能を活用すれば、自宅のWi-Fi契約も見直せます。「楽天モバイル」や「ahamo」「LINEMO」など、自分の使用パターンに合わせた会社を選択するのがポイントです。
格安SIMへの乗り換えを迷う理由として「通信品質の不安」や「手続きの面倒くささ」が挙げられますが、近年は大手キャリアのサブブランドも増え、品質面での差はほとんどなくなっています。
例えば、「ahamo」や「LINEMO」はそれぞれドコモ、ソフトバンクの回線をそのまま使用しており、総務省が実施した2024年度の通信速度調査でも、主要都市部における速度・安定性は大手キャリアとほぼ同等という結果が出ています。
データ使用量が月20GB以下なら、ほとんどのユーザーは月額2,000〜3,000円のプランで十分対応できます。
乗り換え時に注意すべきは「違約金」と「端末の残債」です。2年縛りの違約金は以前10,000円以上かかるのに対して、上限が1,100円とされ、中には無料になるケースも。一方、端末の分割払いが残っている場合は継続して支払う必要があります。
ただし、そのコストを考慮しても、長期的には格安SIMへの乗り換えがお得になるケースがほとんどです。また、家族全員分のスマホ代を見直すと月間の節約額が大きくなるため、家族まとめて乗り換えるのがおすすめです。
スマホの節約は以下記事でも詳しく解説しているので、月々のスマホの料金に悩む方はぜひ読んでみてください。
格安SIMおすすめ10選【2025年最新版】初心者でも失敗しない選び方と比較表付き
サブスク整理: 「サブスク管理表」テンプレートと解約優先度の決め方
マネーフォワードの調査(2023年)によれば、一般家庭は平均7〜8個のサブスクに加入しており、自身が支払っている総額を把握していない人は7割以上。
筆者も実際に「サブスク管理表」を活用して可視化したところ、重複契約や利用していないサービスが数件見つかり、月額6,500円の削減に成功しました。以下の基準で優先度を決めましょう。
2. 月額÷月間利用回数=1回あたりコスト →500円以上なら要検討
3. 類似サービスの重複 → 機能を比較して一本化
サブスクリプションサービスの問題点は毎月自動的に引き落とされ、気づかないうちに支出が膨らむこと。まずはすべてのサービス名、月額料金、契約日、利用頻度を一覧化しましょう。
解約を決断するポイントとして、利用頻度だけでなく生活への影響度も考慮すべきです。例えば動画配信サービスが複数ある場合、同時に契約するのではなく「今月はNetflix、来月はAmazon Prime」というように交代で契約する方法も効果的です。
また、年払いオプションがあるサービスは、月払いと比較して15〜20%程度割安になるケースが多いです。年払いへの切り替えも検討しましょう。
変動費コントロールの実践テクニック

食費節約: 週間献立テンプレートと買い物リスト作成法
食費は工夫次第で30%削減も可能です。週間献立表を作成し、それに基づいた買い物リストで「無駄買い」を防止。さらに「2・2・3ルール」(週2回の作り置き、2回の簡単調理、3回の冷凍・加工食品活用)を実践すれば、時短と節約を両立できます。特売日の把握と季節食材の活用も忘れずに。
効果的な週間献立作成のコツは「食材の連鎖使用」です。例えば、月曜に使う鶏肉の半分を火曜の別メニューに回す、水曜の野菜炒めの余りを木曜の弁当おかずにするなど、食材を無駄なく使い回すプランニングが重要です。また、献立を考える際は「冷蔵庫にある食材から先に使う」という原則を守り、食材廃棄を減らしましょう。
買い物リストは単に必要な食材を書き出すだけでなく、購入店舗と予算上限も記入すると効果的。例えば肉類はディスカウントスーパー、野菜は八百屋など、それぞれの食材に最適な購入先を決めておくことで、無駄な出費を抑えられます。
また、買い物は「空腹時を避ける」という鉄則も重要です。空腹時の買い物は計画外の商品を約25%も多く購入してしまうという研究結果もあります。週末の1時間で次週分の献立と買い物リストを作成する習慣をつければ、平日の食事準備の負担も大幅に軽減できます。
光熱費削減: 電気・ガス・水道別の具体的節約術
日々の暮らしに欠かせない電気・ガス・水道ですが、少しの工夫で大きな節約につながります。まず電気代は「電力自由化比較サイト」を活用して最適なプランに乗り換えるだけで、年間15,000円の削減も可能です。
ガス:シャワー時間1分短縮で月300円、お風呂の追い焚き回数半減で月800円削減
水道:節水シャワーヘッド導入(3,000円)で年間7,000円の節水効果
ガス代はシャワー時間を1分短縮するだけで月約300円の節約に。さらにお風呂の追い焚き回数を半分に減らせば、月に800円前後の削減が可能です。
水道代については、私の実体験で節水シャワーヘッド(約3,000円)を導入したところ、年間約7,000円の節水効果があったのでおすすめです。

これらに加えて、家電の省エネモードを活用したり、冷蔵庫の開閉を減らす使用していない家電の電源プラグを抜くといった日々の小さな行動の積み重ねも重要。
設定温度を1℃見直すだけでも冷暖房費を削減でき、光熱費全体の15%カットも夢ではありません。家族みんなで意識して取り組むことが、継続的な節約のカギです。
▶ 電気代の見直しを本気で考えるなら「Looopでんき」
初期費用ゼロ・基本料金ゼロで、使った分だけ支払うシンプルな料金体系。 「毎月の電気代が高すぎる…」と感じている方は、大手電力会社からの乗り換えだけで月2,000円以上の節約も現実的です。
※利用エリアや契約状況によってはご利用いただけない場合があります
日用品費: まとめ買いとストック管理の具体的方法
日用品はドラッグストアやネット通販の価格を比較表にして、最安値で購入。特に洗剤・シャンプー・ティッシュなどは大容量・詰め替えタイプでまとめ買いし、ストック管理アプリで在庫を可視化。買い忘れと無駄買いの両方を防止します。
また、セール時期やクーポンを活用して購入することで、さらに5〜10%の節約が可能です。日用品は使用頻度が高いため、毎月の支出に直結します。
定期購入サービスを活用するのも一つの手ですが、必要量を把握しないと過剰在庫になるリスクもあるため、月ごとの使用量を記録して管理しましょう。
交際費・娯楽費: 満足度を下げずに節約する方法
「金額÷満足度」で各活動の価値を評価し、低いものから見直し。例えば映画鑑賞なら映画館(1,800円)の代わりにNetflixやAmazonプライムを活用、外食はランチタイム活用(同じ店で夜の70%程度の価格)など、質を落とさず金額を抑える方法を探しましょう。
また、交際費は「人付き合いの質」に注目することも大切です。頻繁な飲み会よりも、価値観の合う人との月1回の食事の方が満足度が高い場合もあります。娯楽も無料イベントや地域の文化施設、図書館などを上手に活用すれば、お金をかけずとも豊かな時間が過ごせます。
収入アップの現実的アプローチ

本業収入アップ:給与交渉と資格取得の費用対効果
給与を上げるには、感情よりも数値で自分の価値を伝えることが重要です。過去6ヶ月間で会社にもたらした成果を、売上や業務効率などの具体的な数字で示し、根拠を持って上司と面談に臨みましょう。
また、資格取得はキャリアアップだけでなく、資格手当で給与を上げてもらえる企業もあるので積極的に挑戦してみましょう。
副業選び:時給換算で効率の良い副業ランキング
オンライン家庭教師:時給1,800円〜
コールセンター:時給1,200円〜1,800円
フリマアプリ・不用品販売:初期投資少なく始められる
ポイントサイト活用:隙間時間で月5,000円程度
副業を選ぶ際の最大のポイントは自分の得意分野を活かせる仕事です。
「得意なスキルが思い当たらない」「少しでも収入を増やしたいけど、何を始めればいいか分からない…」そんな方におすすめなのは、スマホ1台で始められる在宅コール副業です。
この副業の魅力は、資格不要・経験不問で、スマホ・タブレット・パソコンどれでもOK。専用の電話システムを使うので、個人の番号を使うこともなく安心して始められます。
実際のお仕事内容は、お問い合わせへの簡単な対応や、予約の確認など。高額案件も多く、時給換算で2,000円超も夢ではありません。さらにスタッフのサポート付きで、副業初心者でもしっかり稼げる環境が整っています。
月3〜5万円のプラス収入を目指してみましょう。
投資初心者ガイド: 少額から始める堅実な資産形成法
月5,000円からでも始められる積立投資は、将来に備える堅実な手段。特にiDeCoやつみたてNISAは、運用益が非課税になるため税制面で非常に有利です。投資初心者には「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」がおすすめ。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」はモーニングスター社によるファンド評価でも常に高スコアを獲得しており、SBI証券・楽天証券でも人気No.1のインデックスファンドです。
私も毎月の自動積立設定をしていて、価格変動に振り回されずほったらかし投資をしています。メンタル的にもラクです。まずは証券口座の開設と、少額からのスタートがおすすめです。
ポイ活実践術: 家計を圧迫せずポイントを貯める仕組み作り
支出を抑えながらポイントを効果的に貯めるには、普段の買い物を「ポイントサイト経由」に切り替えることがポイントです。楽天市場やYahoo!ショッピングなども経由するだけで還元率がアップします。
光熱費や通信費などの固定費もクレジットカード払いに一本化すれば、毎月自動的にポイントが貯まります。例えば、年間100万円のカード利用で還元率1%なら1万円相当のポイントに。これらを「食費補填」や「レジャー資金」として活用すれば、節約効果と満足度の両方が得られます。
家計管理を継続させるシステム構築

家計簿アプリ徹底比較: 目的別おすすめアプリと設定方法
家計管理がうまくいかない最大の原因は、支出の把握が曖昧なこと。何にいくら使っているかが見えていないと、どれだけ節約しても実感が湧きにくく、継続も難しくなります。
そこで役立つのが、自動で記録・分類・グラフ化してくれる家計簿アプリです。手間なく支出の可視化ができ、日々の支出管理が格段にラクになります。
【目的別おすすめアプリ】
・資産管理向け:「マネーフォワードME」(金融機関連携)
・予算管理重視:「家計簿Zaim」(予算達成率グラフ)
・家族共有向け:「OsidOri」(家族での共有機能)
家計簿アプリをうまく使いこなすには、目的に合ったアプリを選び、最初の設定を丁寧に行うことが重要です。特に銀行口座やクレジットカードと自動連携できるタイプを選べば、手入力の手間が減り、家計の見える化が一気に進みます。
また、1週間ごとに振り返る習慣をつけることで、無駄遣いの傾向や節約ポイントが自然と浮き彫りになります。
予算管理の仕組み: 「貯金先取り」と「変動費の封筒分け」システム
収入を得たらまず目標額を貯蓄し、残りを生活費に回す「貯金先取り」が家計管理の鉄則。手元にあるお金はつい使ってしまうため、先に貯金を分けてしまえば自然と残りでやりくりできます。
変動費は「デジタル封筒分け」で、食費・日用品・交際費などカテゴリごとに家計簿アプリで管理すると便利です。毎週の予算チェックと見直しを習慣にすれば、無意識の支出や赤字も防げ、家計のコントロール力が大きくアップします。
家族の巻き込み方: 旦那や子どもと一緒に取り組む工夫
家計管理が一人の努力に偏ると、長続きしづらくストレスの原因にもなります。旦那さんとは月1回の「家計会議」を開いて、支出の振り返りや来月の目標を共有すると良いです。
子どもには年齢に応じたお小遣い帳や簡単な予算管理を任せ、「お金の教育」の第一歩に。加えて、旅行や外食など、家族全員が楽しみにできる「共通の目標」を設定すると、節約がポジティブなチーム活動になりやすく、家庭全体の意識改革にもつながります。
モチベーション維持: 小さな成功を積み重ねる仕掛けづくり
節約や家計管理は継続こそ命です。そのためには「成果が見える仕掛け」が不可欠。毎月の節約額をグラフ化したり、アプリで達成率を可視化することで、自分の努力が数字として現れます。
目標達成時には「家族で外食」などのプチご褒美を設定しておくと、楽しみながら続けられます。SNSや家族との共有ボードで成果を発信すれば、「応援される仕組み」もでき、三日坊主にならずに節約生活を習慣化することができます。
ママ友に聞いてみた!節約成功者の事例紹介(インタビュー形式)
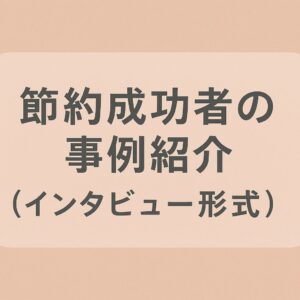
ケース1: 共働き家庭の月10万円節約術(固定費見直し中心)
東京在住のA夫妻(30代)は、住宅ローン借り換えと保険見直しで月3.6万円、通信費とサブスク整理で月2.5万円、光熱費の供給会社見直しで月0.8万円、そして食費の計画的購入で月3.1万円の計10万円の節約に成功。
特に効果的だったのは「すべての固定費を一覧表にして優先順位をつけて交渉した」こと。年間120万円の削減に成功しています。
ケース2: 子育て主婦の食費半減テクニック
3人の子どもを育てるB子さん(40代)は、月7万円の食費を3.5万円に削減。その秘訣は「週末の2時間クッキング」で基本おかずを作り置きし、平日は15分以内で完成する献立にこだわったこと。
また「食材使い切りカレンダー」を作成し、冷蔵庫の食材を無駄にしない工夫も。レシピは無料アプリ「クックパッド」の代わりにYouTubeチャンネルを活用しています。
ケース3: 単身者の光熱費・通信費最小化術
都内在住のC子さん(20代)は、光熱費と通信費を月2.8万円から1.1万円に削減。ポイントは「最小限の契約」と「代替手段の活用」。具体的には大手携帯会社から格安SIMへの乗り換え、自宅Wi-Fi廃止してテザリング活用、電力自由化による新電力への切り替えなどを実施。
帰宅時間が遅い日は近所のカフェで作業してから帰るなど、生活パターンも工夫しています。
成功の共通点: 3つの事例から見えてきた成功の法則
3つの事例に共通するのは以下の3点です。
最初に家計の全体像を把握
削減目標を具体的な金額で設定
定期的な振り返りと改善
特に重要なのは、節約を「我慢」ではなく「最適化」と捉える考え方の転換。無理な節約は続きませんが、生活の質を保ちながらの効率化なら長続きさせることが可能です。
まとめ:物価高時代を乗り切る家計防衛計画

個人的に物価高は当面続くと予想しています。今回紹介した17の節約術と収入アップ法を組み合わせれば、家計への影響を最小限に抑えることが可能です。
特に効果が高いのは「固定費の徹底見直し」「計画的な食費管理」「本業収入のアップ」の3点。まずは今日から、できることから少しずつ始めてみましょう。
一度の大きな変化よりも、小さな習慣の積み重ねが家計を改善します。物価高という「危機」を、家計を見直す「機会」に変えて、より強固な家計基盤を築いていきましょう!
以上、サバイブ家計術編集部からでした。


